目次
企業の成長やプロジェクトの推進には、時に外部の専門的な力が必要となります。即戦力となる人材を柔軟に活用できる「業務委託」は、多くの企業にとって有効な選択肢です。しかし、正社員採用とは異なる点が多く、初めて導入する際には戸惑うこともあるでしょう。この記事では、業務委託採用の基本的な流れから、メリット、注意点までを分かりやすく解説します。
業務委託とは?正社員や派遣との違いを解説
業務委託採用の流れを理解する前に、まず「業務委託」がどのような契約形態なのか、正社員や派遣社員とどう違うのかを正確に把握しておくことが重要です。ここでの理解が、後のトラブル防止に繋がります。
業務委託契約の基本
業務委託とは、企業が特定の業務を外部の法人や個人事業主(フリーランスなど)に委託する際の契約形態を指します。企業と受託者(業務を引き受ける側)は雇用関係を結ばず、対等な立場で契約します。そのため、企業側には社会保険料の負担義務などが生じません。法律上、「業務委託契約」という名称の契約はなく、一般的に「請負契約」と「(準)委任契約」の2種類を総称して使われています。
| 契約の種類 | 報酬の対象 | 業務の完成義務 | 主な例 |
|---|---|---|---|
| 請負契約 | 成果物の完成 | あり | Webサイト制作、記事執筆、システム開発 |
| (準)委任契約 | 業務の遂行(労働時間や行為) | なし | コンサルティング、受付業務、システム保守運用 |
正社員との違い
正社員は、企業と「雇用契約」を結びます。企業は労働者に対して業務上の指揮命令権を持ち、労働者はその指示に従って業務を遂行します。勤務時間や場所は企業の就業規則によって定められます。一方、業務委託では雇用関係がないため、企業は受託者に対して具体的な業務の進め方や時間・場所について細かく指示することはできません。
派遣社員との違い
派遣社員は、派遣会社と「雇用契約」を結び、派遣先企業で業務を行います。業務に関する指揮命令は派遣先企業が行いますが、給与の支払いや社会保険の手続きは派遣会社が担当します。業務委託は、依頼主である企業と受託者の間に基本的に雇用関係がないという点で、派遣とは明確に異なります。(原則として雇用関係はないですが、実態によっては雇用関係とみなされる場合もあります。)
企業が業務委託を採用する3つのメリット
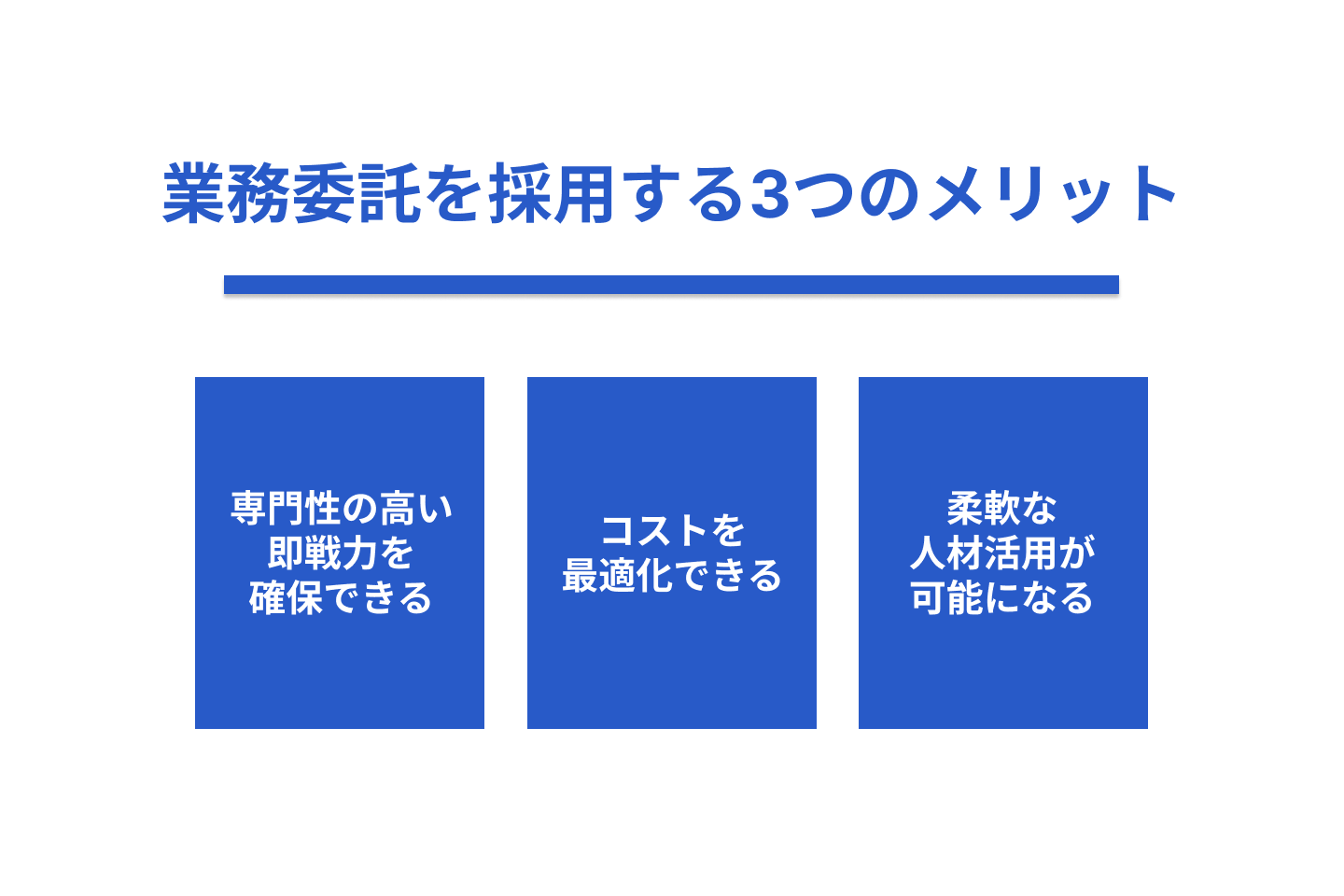
業務委託の活用は、企業に多くのメリットをもたらします。特に変化の速い現代のビジネス環境において、その利点はますます重要になっています。
専門性の高い即戦力を確保できる
業務委託の最大のメリットは、専門的なスキルや豊富な経験を持つ即戦力人材を迅速に確保できる点です。社内で育成するには時間がかかる分野や、一時的にしか発生しない高度な業務に対して、ピンポイントで人材を補強できます。これにより、社員は本来注力すべきコア業務に集中でき、組織全体の生産性向上が期待できます。
コストを最適化できる
正社員を雇用する場合、給与以外にも社会保険料、福利厚生費、通勤交通費、オフィス賃料や備品費など、さまざまなコストが発生します。業務委託では、これらの費用がかからず、契約で定めた報酬のみを支払うため、人件費を大幅に抑えることが可能です。必要な時に必要な分だけ業務を依頼できるため、コストの最適化が図れます。
柔軟な人材活用が可能になる
プロジェクト単位や繁忙期のみといった、短期的なニーズに柔軟に対応できるのも業務委託の利点です。事業の状況に合わせて契約期間を設定できるため、人員の過不足を最小限に抑えられます。これにより、企業は市場の変化に迅速に対応し、機動的な事業運営を実現できます。
業務委託採用の注意点とデメリット
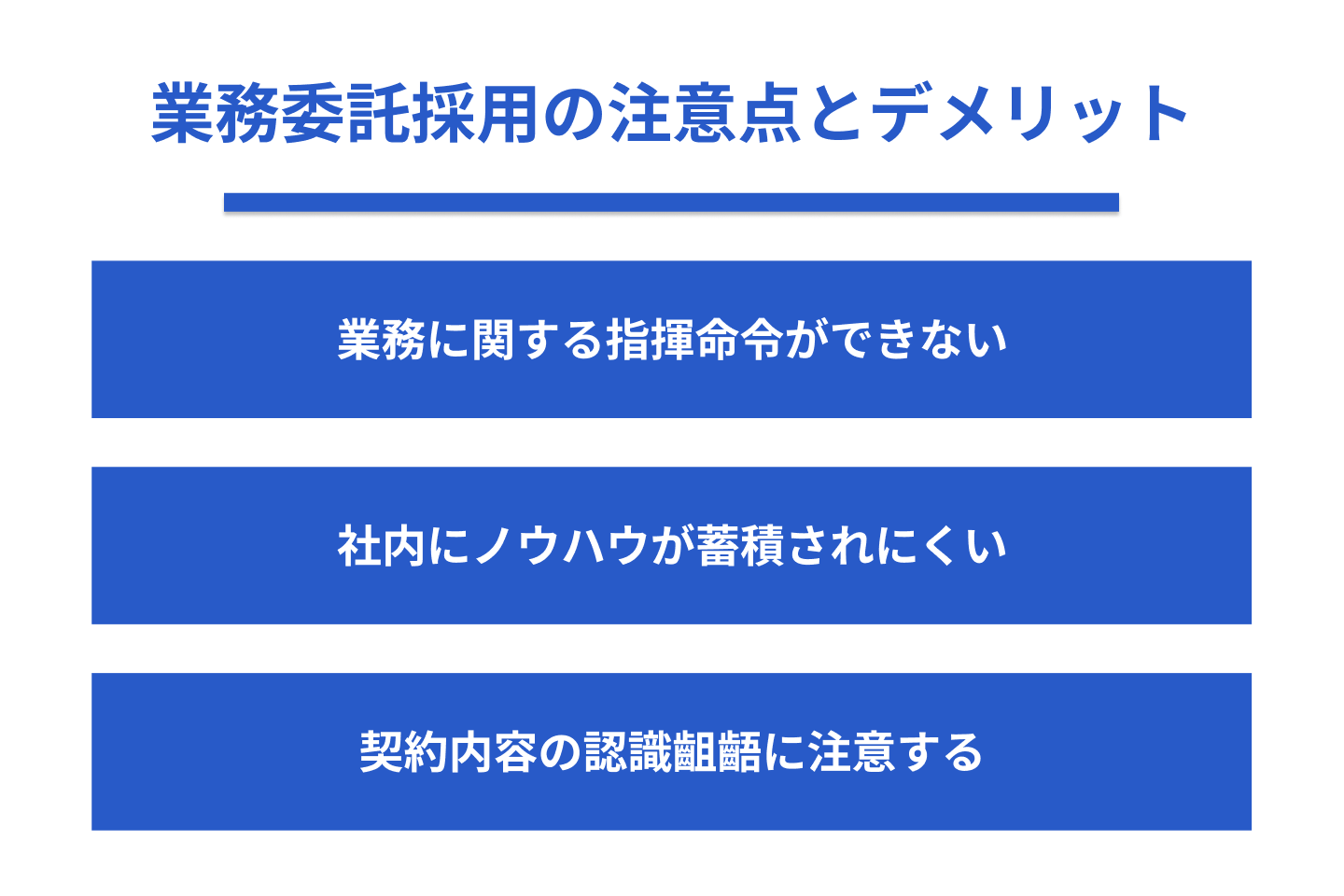
多くのメリットがある一方で、業務委託には注意すべき点も存在します。デメリットを理解し、対策を講じることで、リスクを最小限に抑えられます。
業務に関する指揮命令ができない
前述の通り、業務委託契約では企業と受託者の間に雇用関係が存在しないため、企業は受託者に対して業務の進め方や労働時間、場所などを細かく指示することはできません。これを行うと「偽装請負」と見なされ、法的な問題に発展する可能性があります。業務の進め方は基本的に受託者の裁量に委ねられることを理解しておく必要があります。
社内にノウハウが蓄積されにくい
外部の専門家に業務を委託するため、その業務に関する知識や経験が社内に蓄積されにくいというデメリットがあります。契約が終了すると、そのノウハウも失われてしまう可能性があります。長期的に内製化を目指す業務については、委託先と協力してノウハウを共有する仕組みを作るなどの工夫が求められます。
契約内容の認識齟齬に注意する
業務委託で最も多いトラブルが、契約内容に関する認識の齟齬です。「どこまでの業務を依頼したか」「成果物の基準は何か」「修正は何回までか」といった点を事前に明確に定めておかないと、後々大きな問題に発展しかねません。契約書で業務範囲や成果物の定義を詳細に記載し、双方で合意することが不可欠です。
業務委託採用の具体的な流れ8ステップ
ここでは、実際に業務委託採用を進める際の具体的な流れを8つのステップに分けて解説します。このフローに沿って進めることで、スムーズな採用活動が実現できます。
手順1:依頼する業務と求めるスキルを明確にする
まず、社内のどの業務を、なぜ外部に委託したいのかを明確にします。その上で、その業務を遂行するために必要なスキル、経験、資格などを具体的に洗い出します。「Web広告運用の経験3年以上」「特定のプログラミング言語での開発実績」など、できるだけ詳細に定義することで、採用のミスマッチを防ぎます。
手順2:採用条件(報酬・期間など)を決定する
次に、具体的な採用条件を固めます。報酬体系(固定報酬、時間単価など)、契約期間、稼働時間(週〇時間程度など)、勤務形態(リモート、常駐)などを決定します。特に報酬については、市場の相場を調査し、業務内容に見合った適切な金額を設定することが重要です。
手順3:募集方法を選定し、求人を開始する
条件が固まったら、どの方法で人材を探すかを決め、募集を開始します。募集方法には、求人サイトや業務委託専門のマッチングサイト、知人からの紹介など、さまざまな選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合った方法を選びましょう。
手順4:応募者対応と書類選考を行う
募集を開始すると、候補者から応募があります。応募があった際は、迅速かつ丁寧に対応することが重要です。提出された履歴書や職務経歴書、ポートフォリオなどをもとに、手順1で定めたスキル要件を満たしているかを確認し、書類選考を行います。
手順5:面談を実施し、スキルと人物像を見極める
書類選考を通過した候補者と面談を行います。面談では、提出書類だけでは分からない実績の詳細や、具体的なスキルレベルを確認します。また、コミュニケーションの取り方や仕事への価値観など、自社のカルチャーに合う人物かどうかも見極める大切な機会です。
手順6:採用を決定し、条件交渉を行う
面談を経て採用したい人材が決まったら、採用の意思を伝えます。その際に、報酬や業務範囲、契約期間などの条件について、最終的なすり合わせを行います。ここでお互いの認識を一致させておくことが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
手順7:業務委託契約書を作成・確認する
条件交渉で合意した内容をもとに、業務委託契約書を作成します。契約書には、業務内容、報酬、納期、成果物の権利の帰属、秘密保持義務など、重要な項目を漏れなく記載します。作成した契約書は、弁護士などの専門家に確認してもらうとより安心です。
手順8:契約を締結し、業務開始の準備を進める
双方が契約書の内容に合意したら、署名・捺印をして契約を締結します。契約締結後は、業務に必要な情報(各種アカウント、資料など)を共有し、スムーズに業務を開始できる環境を整えます。
スタートアップ企業に特化した採用戦略についても気になる方は、下記記事をご覧ください。
【関連記事】スタートアップの採用戦略を徹底解説!成功に導く5つのポイントとは?|Hitorime
業務委託の募集方法4選
求める人材に出会うためには、適切な募集方法を選ぶことが不可欠です。ここでは代表的な4つの方法を紹介します。
| 募集方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 求人サイト | 多くの人に見てもらえる可能性がある | 応募者の質にばらつきがある、掲載費用がかかる場合がある |
| 業務委託マッチングサイト・エージェント | 業務委託希望者が多く、効率的に探せる | マッチング手数料が発生する場合がある |
| クラウドソーシング | 手軽に募集できる、多様な人材が見つかる | スキルの見極めが難しい場合がある |
| リファラル | 信頼性が高い、採用コストを抑えられる | 人材が見つかるとは限らない、人間関係に配慮が必要 |
求人サイト・求人検索エンジン
正社員採用で馴染みのある求人サイトや求人検索エンジンでも、業務委託の募集は可能です。幅広い層にアプローチできる可能性がありますが、業務委託での働き方を希望していないユーザーも多いため、雇用形態を明確に記載する必要があります。
業務委託マッチングサイト・エージェント
フリーランスや副業ワーカーなど、業務委託を希望する人材が登録している専門のマッチングサイトやエージェントを利用する方法です。求めるスキルを持った人材を効率的に探せる可能性が高いですが、採用が決定した際に手数料が発生することが一般的です。
クラウドソーシングサービス
仕事を依頼したい企業と、仕事を探している個人をオンラインで繋ぐサービスです。単発の小さな業務から長期的なプロジェクトまで、様々な案件を依頼できます。多くの登録者がいるため人材を探しやすい反面、スキルの見極めは慎重に行う必要があります。
リファラル(知人紹介)
社員や取引先など、信頼できる人からの紹介で人材を見つける方法です。採用コストを大幅に抑えられる上、紹介者の信頼があるためミスマッチが起こりにくいというメリットがあります。ただし、紹介に頼るため、必要なタイミングで必ずしも適切な人材が見つかるわけではありません。
スタートアップ企業のリファラル採用について気になる方は、下記記事をご覧ください。
【関連記事】スタートアップこそリファラル採用を!成功に導く具体的な手順と注意点を解説|Hitorime
契約時に確認すべき重要ポイント
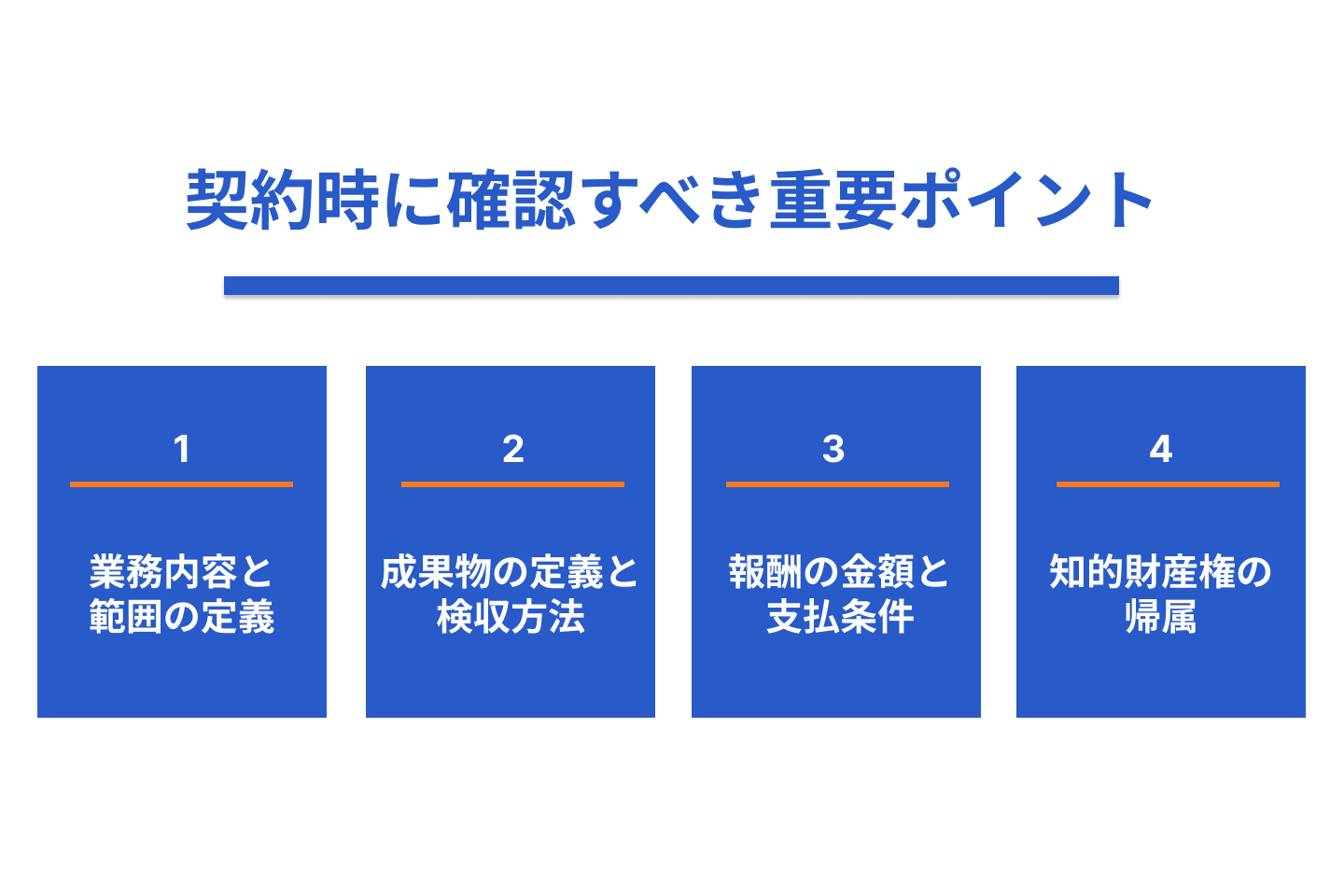
業務委託契約書は、採用における最も重要な書類です。後々のトラブルを避けるため、特に以下の4つのポイントは必ず確認し、明確に記載しましょう。
業務内容と範囲の定義
「コンサルティング業務」「Webサイトのデザイン業務」といった曖昧な表現ではなく、「月次でのSEOキーワード分析とレポート提出」「トップページ及び下層3ページのデザインカンプ作成」のように、誰が見ても分かるレベルまで具体的かつ詳細に業務内容と範囲を記載します。
成果物の定義と検収方法
請負契約の場合、何を以て「成果物」とするのかを明確に定義します。また、納品された成果物をどのように確認し、問題がなければ驗収完了とするのか、修正依頼は何回まで可能かといった検収のプロセスも具体的に定めておきます。
報酬の金額と支払条件
報酬の金額、計算方法(固定、時間単価など)、消費税の取り扱い、支払いサイト(月末締め翌月末払いなど)、支払い方法(銀行振込など)を明記します。経費が発生する場合、その負担についても取り決めておきましょう。
知的財産権の帰属
制作された成果物(デザイン、プログラム、文章など)の著作権をはじめとする知的財産権は、法的には原則として創作者である受託者に帰属します。報酬の支払いのみでは自動的に依頼主である企業側に権利が譲渡されることはないため、権利の帰属や譲渡について契約で明確に定める必要があります。
まとめ
業務委託採用は、正社員採用とは異なる流れや注意点が存在しますが、そのプロセスを正しく理解し、一つ一つのステップを丁寧に進めることで、企業にとって強力な人材活用の手段となります。本記事で解説した流れとポイントを参考に、自社の成長を加速させる最適なパートナーを見つけてください。
スタートアップ採用で1人目人材を見つけるなら、Hitorimeがおすすめです。
1人目ポジション特化の採用マッチングサービスで、エンジニアやCxO、新規事業責任者など重要なポストの人材と効率的に出会えます。募集掲載からスカウト機能まで基本利用料は無料のため、採用活動をコストを抑えながら加速できます。


